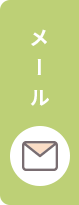みんな
心理指導担当職員のぼやき VOL.32 ~恥ずかしいという気持ちを考える~ 札幌市東区 児童発達支援・放課後等デイサービス てとり・てとりキッズ・てとりplus

ご無沙汰しています。この投稿も2年ぶりとなっていました。
てとりグループでは月に1度、療育に必要な知識や技術を身に付けることを目的に職員研修を実施しています。
今年度は『羞恥心』や『羞恥感情』というものに焦点を当てて、数回に分けて研究・実践を積み上げていこうと考えております。
これをお読みになっている皆さまにも1度は「恥ずかしい。」と羞恥経験をしたことはあるのではないでしょうか?
どんな時でしょう?人前で転んでしまった時でしょうか?それとも人前で発表しなければいけない時でしょうか?
『恥ずかしさ』に関する研究は、欧米では注目されており、「shyness(シャイネス)は、心の健康被害を与える可能性がとてもある。」とされています。
「恥ずかしさ」を理由に、社会生活を営むための行動を抑制させてしまい、結果的に自尊感情や自己肯定感等に影響を与えてしまいます。
私たち日本人は恥ずかしいと思いがちです。
統計に基づいても、日本人は諸外国に比べて羞恥心が高いというデータがあります。
また、自分の気持ちや考えよりも、相手の気持ちや考えを深く読み取り、自分より相手を尊重することも、“美徳”とされてきました。
そう考えてみると、『恥ずかしさ』を考えるには、その場所の文化的背景は非常に大切になってくるため、諸外国のように、「恥ずかしいという理由から自己表現ができないのは心の健康に悪い。」とは一概には言えませんね。
また、『恥ずかしさ』が非行の抑止に繋がっているという研究データもあります。非行行動を抑止する条件は何かを、トルコ人の中高生と日本人の中高生で比べたところ、日本人の中高生にだけ自分の行動に対しての恥意識が、非行を抑止できたというデータもあります。悪い事だけではないのです。
しかし、恥ずかしいという気持ちが強すぎて社会的な行動が阻害されるのは良くありません。
この、恥ずかしいという気持ちと上手く折り合いをつけたいものです。
恥ずかしいという気持ちは、【出来事に対する認知的評価の中で、最終的に自己への帰属によって生起する事を踏まえ、自己意識の成立を経て羞恥心も出現し始める】そうです。
何だか難しいですが、要するに、自分の身の回りに起きた出来事に対して、誰のせいにもすることができなくなり、「自分が悪いのか。」となった際に、恥ずかしさを覚えるようです。
そう考えてみると、「人のせいにばかりしている人ほど、羞恥心が強い。」という図式も成り立つかもしれません。
それ以外でも『恥ずかしさ』を研究しているものは多く、「委員や係活動の責任が果たせない」ことに対して、小学校4年生の男子は80%が“恥ずかしいこと”と回答していますが、小学校5年生の男子は47%しか“恥ずかしいこと”と答えなくなります。
そして「決まりを守らない」という質問に対しては、“恥ずかしいこと”と答える人が最も少なかったようです。
従って、成長に従って『恥ずかしさ』も質的に変化していくようです。
研修の後半は、各施設に分かれてディスカッションをしました。
「ルールを守らないことに『恥ずかしいことだよ。』とか声かけていたけど、関わり間違えていたかもしれない。」といった意見が出たり、「どんな言葉を使えば、子どもの心に届くだろう?」等といった具体的な話題も出て有意義な時間となりました。
通年で、私たちは『恥ずかしさ』に関して学びを深めていき、各施設にあった療育活動を考えていくことにしております。また実践報告ができればなと思います。
児童発達支援放課後等デイサービス てとり
心理指導担当職員 松本